この記事で分かること
- 短期間育休(1〜3ヶ月)と1年間育休の体験の違い
- 1年間育休で見られる子どもの成長全記録
- 育休1年間のリアルなメリット・デメリット
- 期間選択で後悔しないための判断基準
育休を取ると決めたあなた、おめでとうございます!
でも今、「どのくらいの期間取ろう…」と悩んでいませんか?
「会社の先輩は3ヶ月だったし」 「1年は長すぎるかも」 「収入面が心配…」
実は、あなたの悩みは多くの男性が抱える共通の課題なんです。
2024年度の調査によると、若い男性社会人の7割が1カ月以上の育休取得を希望しているのに対し、実際に育休を取得した人の6割は1カ月未満という現実があります。
参考:https://times.abema.tv/articles/-/10199564?page=1
つまり、多くの人が「本当はもっと長く取りたい」と思いながら、短期間で妥協している状況なのです。
私も全く同じ悩みを抱えていました。
結論から言うと、私は1年間の育休を取得し、人生で最も価値のある1年を過ごすことができました。
この記事では、実際の体験を基に短期間育休と1年間育休の「本当の違い」をお伝えします。最後まで読めば、あなたにとって最適な期間選択ができるはずです。
なぜ多くの男性が短期間で妥協するのか?
現在の男性育休取得の実態
2024年度の調査によると、男性の育休取得率は40.5%と過去最高を記録しました。しかし、その取得期間については未だ問題があるといえます。
希望と現実の大きなギャップ
- 希望:若い男性社会人の70%が「1ヶ月以上取りたい」
- 現実:実際の取得者の60%が「1ヶ月未満」で終了
短期間取得した場合にどうなる?
多くの男性が選択する1〜3ヶ月。でも、実はこの期間で復職すると…
見逃してしまう「初めて」の瞬間たち
1ヶ月で復職した場合
- ❌ 初めての笑顔(生後2〜3ヶ月)
- ❌ 首がすわる感動的瞬間(3〜4ヶ月)
- ❌ 寝返りの成功(4〜6ヶ月)
3ヶ月で復職した場合
- ❌ お座りができた日(6〜8ヶ月)
- ❌ 離乳食を初めて食べた顔(5〜6ヶ月開始)
- ❌ つかまり立ちへの挑戦(8〜10ヶ月)
- ❌ 初めての「パパ」(10〜12ヶ月)
※上記はあくまで目安の成長であり、赤ちゃんによっては発育が遅い場合もあります。記載されている月齢でできていなくても、ほとんどの場合は単なる個性です。
ママの負担が続く現実
産後1ヶ月時点のママの状態:
- 悪露が続いている可能性
- まだまだ睡眠不足でフラフラ
- 体調もホルモンバランスも不安定
産後3ヶ月時点のママの状態:
- 体力は7割程度回復
- でも夜泣きはまだまだ続く
- 寝返りや外出なども増え、一人での育児負担が増加
こちらも各家庭の状況は様々ですが、初めての子育てを旦那が職場で働いている時間にずっと独りで頑張らなければいけません。
これが短期間育休の現実です。
【実録】1年間育休で体験した成長の瞬間
月齢別・感動体験レポート
ここからは実際に感じた我が子の成長についてお話します。
0〜2ヶ月:「生命」を肌で感じる新生児期
身体の成長
- 体重:出生時から1日25〜50g増加
- 睡眠:昼夜の区別なく2〜3時間おきに起床
ぶかぶかのベビー服にくるまっている赤ちゃんはこの時しか見られません。
この時期に体験できること:
- 原始反射(把握反射、吸啜反射など)の観察
- 夜中の授乳を妻と交代制で実施
- 沐浴を毎日担当し、スキンシップ増加
3〜4ヶ月:「笑顔と首すわり」の感動期
身体の成長
- 首がすわり始める(3〜4ヶ月)
- 社会的微笑が始まる(2〜3ヶ月)
- 昼夜のリズムが整い始める
初めて家族そろって帰省し、初孫、初ひ孫に喜ぶ親戚一同。赤ちゃんがいるだけでその場が明るくなるのを感じました。
この時期に体験できること:
- 人生初の笑顔を目撃
- 首すわりの練習サポート
- あやし方のコツを習得
5〜6ヶ月:「寝返りと離乳食開始」の挑戦期
身体の成長
- 寝返りができるようになる(4〜6ヶ月)
- 離乳食開始(5〜6ヶ月)
- お座りの練習開始
何度も寝返りしそうになっては、慌ててスマホで動画を撮ろうとして、なかなか成功しなくて。
そうして初めて成功したときは夫婦二人で「おめでとう!」と喜びました。
(子どもは早く戻せ!って感じで泣いてしまいましたが……)
この時期に体験できること:
- 寝返り成功の決定的瞬間に立ち会い
- 離乳食作りから食べさせまで全て経験
- 成長に合わせた安全対策の実施
7〜8ヶ月:「お座りとずりばい」の自立への一歩
身体の成長
- 支えなしでお座りができる(6〜8ヶ月)
- ずりばいが始まる(7〜8ヶ月)
- 人見知りが始まる時期
なかなかずりばいが出来なかったけれど、他の赤ちゃんの動きを見て理解したのか、次の日から少しずつできるようになって驚きました。
9〜10ヶ月:「はいはいとつかまり立ち」の運動能力向上期
身体の成長
- はいはいが上達(8〜10ヶ月)
- つかまり立ちを始める(8〜10ヶ月)
- 指先の細かい動きが発達
この時期に体験できること:
- 家の中を探検する姿を見守り
- 安全対策の重要性を実感
- 好奇心旺盛な姿に感動
11〜12ヶ月:「言葉の芽生えと1歳の節目」感動のクライマックス
身体の成長
- つたい歩きから一人歩きへ(10〜15ヶ月)
- 意味のある言葉を話し始める(10〜12ヶ月)
- 手づかみ食べが上達
1年間で目撃できる成長:
- 体重:約3倍に増加(3kg→9kg程度)
- 身長:約1.5倍に成長(50cm→75cm程度)
- できること:寝ているだけ→歩く・話すまで
1年間育休の「本音のデメリット」
経済面の現実
長期の育休で特に不安に感じてしまうのが収入面だと思います。不安に感じる原因はよく知らないから、ということであれば、実際の我が家の家計について載せておきます。
我が家の収入変化(実例)
- 育休前の平均手取り月給:約31万円
- 育休中の給付金:約25万円→半年後→約19万円
- 実質減収:▲約6~12万円
分かりやすく月々の手取りで記載しましたが、やはり育休前と同じ生活水準とはいきません。
さらに詳細な金額や子育て費用などについては、別記事「[育休中のお金事情]」で詳しく解説していますので、良ければ参考にしてみてください。
キャリアへの影響
育休を一年間取得したい旨を会社に伝えた時には、やはり最初は少し驚かれてしまいました。
けれど、会社側はすぐに自分の意見を尊重し、現場との調整であったり、給付金の手続きなど様々な面で多くの方々に後押ししてもらいました。
実際に感じた不安
- 会社に迷惑をかけてしまうのでは……
- 一年後に会社復帰できるだろうか……
実際に取得した結果
- 仕事の引き継ぎをしっかり行って問題なく現場を離れられた
- 会社の方々はむしろ育休を後押ししてくれた
- 育休中に勉強してスキルアップを目指したが、普通に忙しくて無理だった
「[妊娠が分かってから育休開始まですること]」でその時の流れや手続きの期限について記載しているので、会社に応援されながら皆さんも育休に入っていければと思います。
社会的孤立感
人によっては平日に他の人が働いている中で自分だけ会社勤めから離れているのに、孤独感を感じる人がいるかと思います。
もちろん業種にもよりますが、同期や友達と予定を合わせづらくなったり、家事育児で人とあまり喋らずにいると精神的にも悪影響を及ぼします。
特に父親は、場所によっては授乳室に入れなかったり、育児セミナーや赤ちゃん会での男女比で肩身が狭い思いがしやすい。自分も育休中はよく感じていました。
それでも1年間をおすすめする「決定的理由」
理由①:夫婦の絆が圧倒的に深まる
子どもは毎日成長します。
できることはどんどん増えますし、親がしなければいけないことも増えていきます。
- 哺乳瓶でミルクをあげていたかと思えば、離乳食が始まります
- 落ち着いて沐浴を入れていたかと思えば、浴室でも寝返りするようになります
- テープタイプのオムツを使っていたはずが、気が付けばパンツタイプを使うようになります
月日が経つごとに子どもの行動範囲は広がり、育児の忙しい差も上がっていきます。
だからこそ、短期的な育休取得では意味がないと私は考えています。
育児のストレスや大変さを長期間にわたって分かち合うことで、夫婦の結束力が高まり、今後の人生の困難にも一緒に立ち向かえる基盤ができます。
理由②:子どもとの絆が圧倒的に深まる
1年間毎日一緒にいることで、子どもの個性、好み、癖を完璧に理解できるようになります。
子どもの成長を見逃すことなく、一生に一度の時間を過ごすことで子どもとの絆をより深められます。
確かに子どもは0歳児の記憶は忘れてしまうかもしれません。しかし親であるあなたはきっと、この育休の日々を一生忘れないでしょう。
【判断基準】あなたはどちらを選ぶべき?
ここまでで短期間育休、一年育休それぞれのメリット、デメリットについて記載してきました。それを踏まえて、どちらを選択すればよいか下記にまとめました。
短期間(1〜3ヶ月)がおすすめな人
- 日々の生活費が高く、どうしても収入を下げられない
- キャリア形成の重要な時期
- 会社の制度・風土が整っておらず、会社の理解が得られていない
- パートナーが育児に自信がある
1年間がおすすめな人
- 子どもとの時間を最優先にしたい
- パートナーと真の協力関係を築きたい
- 今しかできない経験をしたい
- 職場の育休文化向上に貢献したい
まとめ:統計が示す現実と、あなたの選択
2024年の調査で明らかになったように、多くの男性が「もっと長く育休を取りたい」と思いながら短期間で妥協している現実があります。
でも、その現実を変えられるのはあなたです。
こちらのサイトでも記載されていますが、育休取得は周りに波及します。
https://times.abema.tv/articles/-/10199564?page=3
あなたが1年間の育休を取得することで:
- 同僚が育休を取る確率が上昇
- 職場全体の育休文化が改善
- 後輩たちが安心して長期取得できる環境作り
1年間の育休には確実にリスクがあります。 でも、得られるものはそれ以上に大きいというのが私の結論です。
そして、統計が示すように、あなたと同じように「本当はもっと長く取りたい」と思っている男性がたくさんいるのも事実です。
最も大切なのは:
- 夫婦でとことん話し合うこと
- 経済面のシミュレーションを行うこと
- 会社との調整を丁寧に行うこと
- 覚悟を決めて取り組むこと
- あなたが職場の育休文化を変える先駆者になること
あなたはどちらを選びますか? そして、あなたの選択が与える影響を考えてみませんか?
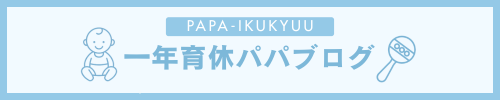
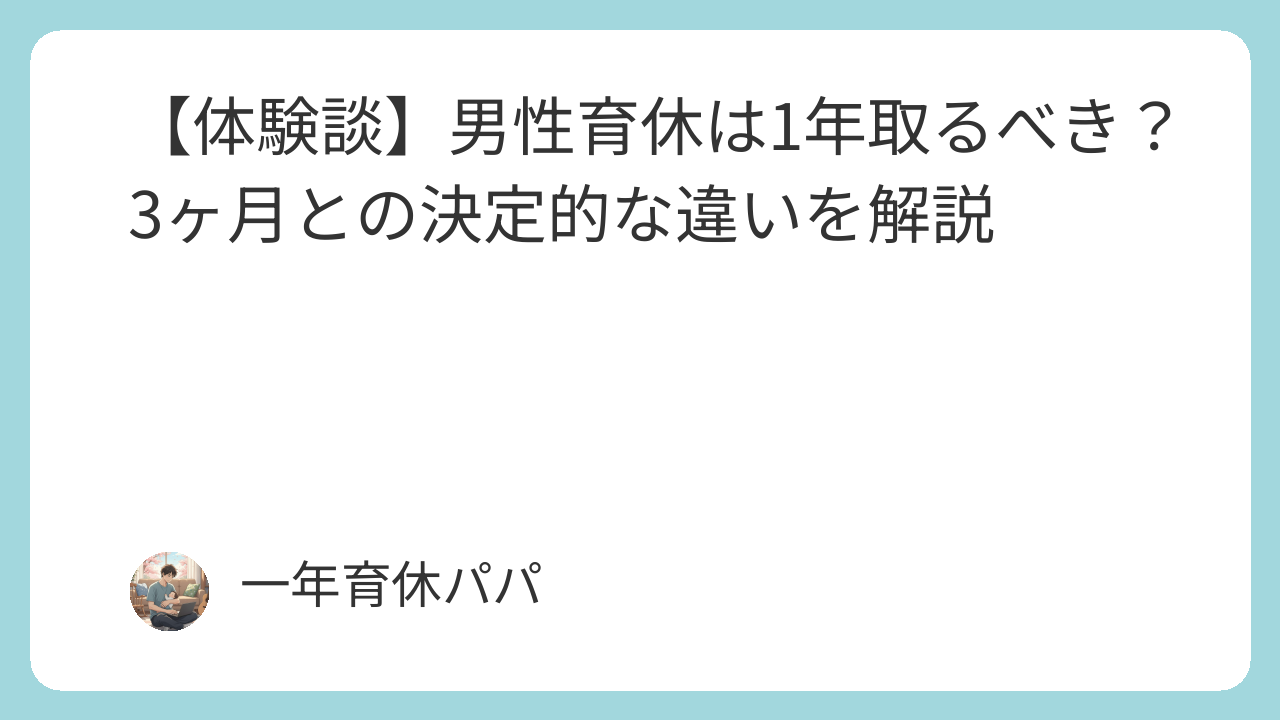
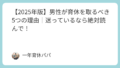
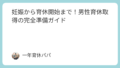
コメント