はじめに:妊娠が分かったパパへ
妊娠が分かって喜びと同時に「育休を取りたいけど、何から始めればいいの?」と不安になっていませんか? 会社にいつ、どのように伝えればいいのか、手続きはいつまでに済ませればいいのか、ネットで調べても具体的なタイミングが分からず困っている方も多いのではないでしょうか。
この記事では私が実際に会社員として育休を取得した経験をもとに、妊娠が分かってから育休開始まで「いつ」「何を」すればいいのかを、出産予定日を基準とした逆算スケジュールで詳しく解説します。特に会社への報告タイミングや各種手続きの期限について、実体験を交えてお伝えするので、同じように悩んでいるパパの参考になれば幸いです。
妊娠発覚~出産予定日8ヶ月前:妊娠が分かったらまずすること
妻との話し合いが最優先
妊娠が分かったら、まずは妻と育休取得についてしっかりと話し合いましょう。取得の意向、期間、家事・育児の分担など、二人で方向性を決めることが重要です。
私の場合は、妊娠前から育休を取るなら長く取りたいという話をしており、妊娠が分かった翌週には「1年間の育休を取りたい」という意向を妻と共有しました。
会社の育休制度を確認
次に、自分の会社の育休制度について調べます。就業規則や人事部の資料を確認し、以下の点をチェックしましょう:
- 育休取得可能期間
- 申請の期限
- 必要な書類
事前に内容について確認しておくことで、実際に会社の人に相談する際に、よりスムーズに話を進められます。
また基本的には育休制度は国の法律で定められている基準があるのですが、普通の会社であればそれに沿った形で就業規則を作成しているはずです。
もし明らかに不利な条件があるようだったら、念のため厚生労働省のホームページを確認し、自社の人事に相談しましょう。
参考:厚生労働省「育児・介護休業法について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html (2024年1月時点の情報)
早いうちに最初の報告
妊娠が確定し、妊婦検診で病院へ付き添いで行く回数が増え始めた頃(妊娠2~3ヶ月)に、まずは担当営業(いわゆる自分の管理者的な立ち位置の方)に報告しました。この時点では「病院への付き添いで有給を使う旨」と併せて「妊娠の報告」と「育休取得の意向」を伝えました。
なお、普段から有給取得や事務連絡をする際はメールで行っていたため、この時の連絡もメールで行いました。だた、伝えたい内容が複雑であったり、電話のほうが早いと感じたときは、以降の連絡で適宜電話したりもしました。
私の場合の報告内容:
- 妻の妊娠報告
- 出産予定日(重要!)
- 育休取得を考えている旨
- 期間は一年で考えている旨
- 詳細な期間は後日相談したい旨
担当営業の反応と対応
担当営業には「おめでとう!育休については会社として応援するから、詳細が決まったらまた相談しよう」と言ってもらえました。また以降の対応では担当営業を中心に、自社の管理部門や現場責任者への伝達などを行いました。ここで重要なのは、育休取得への理解を早めに得ておくことです。
特に私の場合は、SESという特殊な働き方のため、自社の理解と現場の理解の両方を得ることが重要でした。そのためなるべく早く自分の意志を伝えることで、余裕をもって現場での引き継ぎや退場手続きを行えるようにしたことが、結果的にはよかったのではないかと考えます。
出産予定日7~6ヶ月前:現場のチームメンバーへの報告
チームメンバーへの段階的な報告
妊婦検診への付き添いで度々休みを取っていたため、チームメンバーにも報告を行いました。なお、プロジェクトマネージャー(現場責任者)には事前に自社の担当営業から既に伝えられている状態だったのですが、それがどこまで話が広がっているのか不明だったため、この段階では以下のような内容で報告しました:
- 妻の出産予定日
- 育休取得予定(期間は未確定)
- 業務の引き継ぎについて今後相談したい旨
出産予定日5~4ヶ月前:具体的な期間決定と管理部門への相談開始
育休期間の正式決定
この頃までに、育休の具体的な期間を決定しました。私の場合は「出産日から1年間」と決定し、改めて現場のメンバーにも報告しました。
管理部門と相談
自社の管理部門に育休申請で必要な手続きについて確認しました。この時点で以下を確認:
- 申請書類の種類と提出期限
- 給付金の手続きについて
育休中の給付金については、管理部門の方が事前に自分の直近の収入をもとに、想定金額を調べてくださったため、それを参考に育休中の家計管理を計画することができました。詳しくは、別記事「[育休中のお金事情]」で詳しく解説していますので、良ければ参考にしてみてください。
特に管理部門と申請について確認のやり取りを行ったのが、申請書類に記載する「育休の取得期間」でした。申請時点で子どもはまだ産まれていないにもかかわらず、開始日をどうやって書けばよいのかが自分の中で腑に落ちず、何度も確認を行いました。
結果として、出産予定日をいったん書いておいて、産後に改めて開始日を訂正して申請しなおすことで、無事に育休に入ることができました。
出産予定日3ヶ月前:チームへの報告と業務調整開始
業務の棚卸しと引き継ぎ計画
担当業務の棚卸しを開始し、どの業務を誰に引き継ぐか、どのタイミングで引き継ぎを完了させるかの計画を立て始めました。特に長期プロジェクトについては、早めの調整が必要です。
出産予定日2ヶ月前:書類提出と本格的な引き継ぎ開始
必要書類の準備
管理部門から指示された書類を提出:
- 育児休業申出書
- その他会社指定の書類
法律上、育休開始日の1ヶ月前までに申請が必要です。念のため余裕を持って提出しておきましょう。
業務引き継ぎの本格化
この時期から本格的な引き継ぎを開始。私が実際に行った引き継ぎ内容:
- 担当プロジェクトの進捗状況整理
- クライアントとの関係性の引き継ぎ
- 定期業務の手順書作成
- 緊急時の対応方法の共有
出産予定日1ヶ月前:最終調整
引き継ぎの最終確認
引き継ぎ相手と最終確認を実施。引き継ぎノートの完成と、実際の業務を一緒に行いながらの OJT を実施しました。
また予定日一か月前であっても、陣痛が始まることもあるため、事前に陣痛タクシーの予約や産後入院の準備、急な早退でも対応できるようにチームメンバーへの共有をしっかり行いましょう。我が家の場合は、予定日の約10日前に産まれました。
出産:いよいよその時が!
出産時の会社連絡
出産直後に連絡しなければいけない人は会社の人ではありません。
まず妻の両親、その次に自分の両親に連絡してください!
そのあとで落ち着いてから会社の人や現場の人などに連絡しましょう。自分の場合は金曜の夜だったこともあり、週明けに担当営業と管理部門に連絡しました。出産日が確定することで、正式な育休開始日も確定します。
連絡内容:
- 出産日時
- 母子の状況
- 育休開始日の確定
- 最終出社日の調整
出産後~育休開始まで:現場の最終引き継ぎと退場
最後の数日間
出産後、数日間は母子ともに入院したため、その間に会社に出社して最終的な引き継ぎを行いました。この期間にしたこと:
- 残務の整理と引き継ぎ
- チームメンバーへの挨拶
- デスクの片付け
- PCやID カードなどの返却
また早退を使って妻と子どもの面会にも足を運びました。この頃にはほとんどの作業の引き継ぎが完了していたおかげで、時間的余裕があったと思います。
育休開始日の調整
母子の退院日に合わせて育休開始日を調整し、業務に支障がない形で育休をスタートしました。
育休開始:新生活のスタート
育休開始初日
退院する母子を迎えて、ついに育休開始!
日々の奮闘については他の記事を読んでいただければと思います。
まとめ:早期の報告と計画的な準備が成功の鍵
男性の育休取得は、早いうちから情報共有しておくことと、計画的な準備が成功の鍵です。特に重要なポイントをまとめると:
タイミング別のポイント
- 8ヶ月前:妻との話し合い、会社制度を確認し担当へ報告
- 7~6ヶ月前:チームへの報告
- 5~4ヶ月前:期間決定、管理部門との相談開始
- 3ヶ月前:チームへの報告と業務調整開始
- 2ヶ月前:書類準備、引き継ぎ本格化
- 1ヶ月前:最終調整
- 出産後:現場退場と育休開始
成功のコツ
- 妻と事前に十分な話し合い
- 早めの報告と相談で理解を得る
- 期限を過ぎないように余裕を持って申請
- 丁寧な引き継ぎで職場への配慮を示す
男性の長期育休取得はまだまだ珍しいかもしれませんが、早期で計画的に準備すれば必ず実現できます。この記事が、育休取得を考えているパパの背中を押すきっかけになれば嬉しいです。育休は家族にとって大切な時間。ぜひ積極的に取得を検討してみてください!
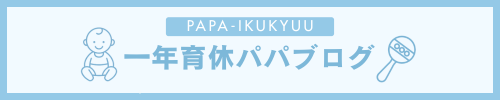
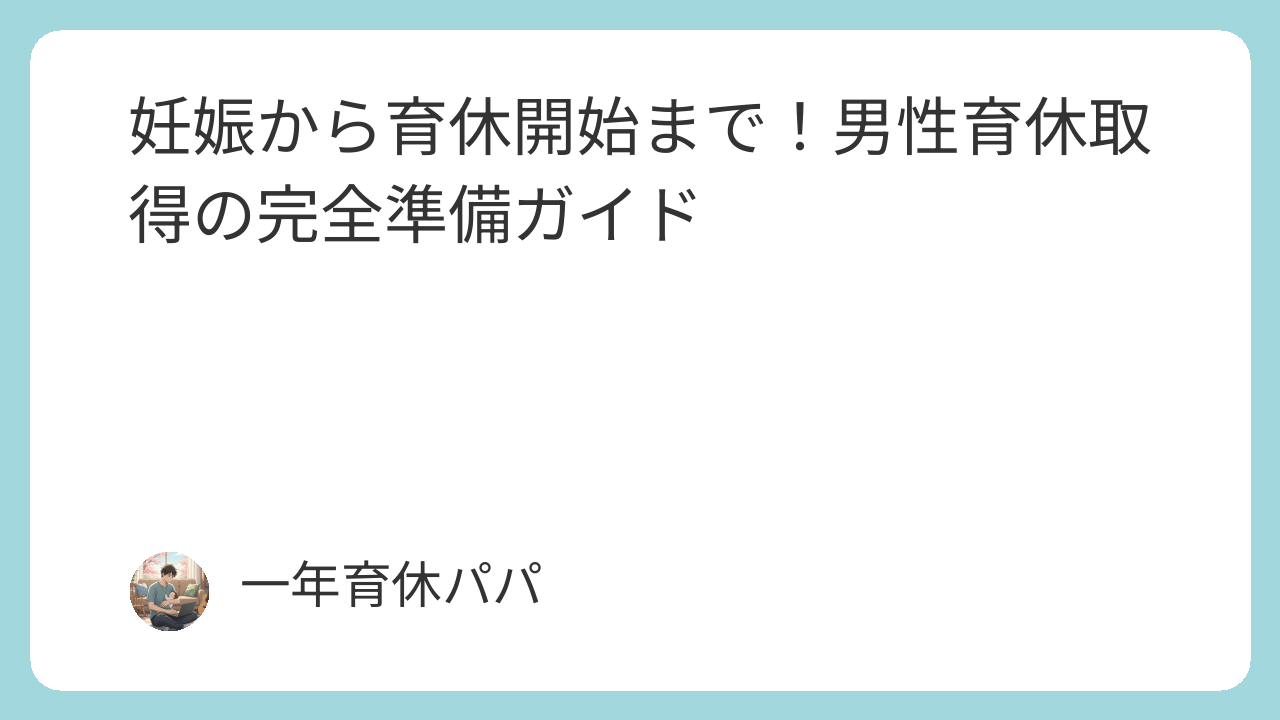
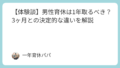
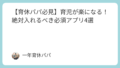
コメント